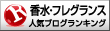「本のレビュー」では読んで興味深かった本を紹介しています。直接編集・翻訳にかかわった作品については「ライター部屋」へ。
今回のレビューは『エリザベート ハプスブルク家最後の皇女』(塚本哲也著、文藝春秋)について。
「ハプスブルク家」の「エリザベート」ですが皇帝フランツ=ヨーゼフの妃シシィのことではありません。この本の主人公は、その孫娘です。
同名の祖母同様に美貌かつ奔放なお姫さまですから、ドラマチックな展開は保証つき!
大宅壮一ノンフィクション賞受賞作品。
本書を原作にマンガ化した『エリザベート』(水野英子画)もあります。
父ルドルフ、愛人と情死
エリザベート(1883~1963)はオーストリア皇太子ルドルフとベルギー王女ステファニーの娘。
皇帝である祖父フランツ=ヨーゼフにかわいがられながら育ったお姫様ですが、父ルドルフは皇太子でありながら愛人と心中してしまいます(マイヤーリンク事件)。
事件については1936年にフランスで映画化されていて、邦題は「うたかたの恋」。
映画ではロマンスと「情死」の部分が強調された演出になっていますが、ルドルフの死は多分に政治的なものだったようです。開明的なルドルフは保守的で頑迷な父フランツ=ヨーゼフとことあるごとに対立していました。
エリザベートの恋と結婚と離婚と結婚
イケメン軍人に一目惚れ
年頃になったエリザベートは宮廷舞踏会で見目麗しい軍人オットー・ヴィンディシュ=グレーツに一目惚れ! しかし身分の低い相手なので「貴賤結婚」となります。
オットーも由緒正しい貴族なのですが、皇帝家とはつりあわない「下級貴族」でした。
皇帝は孫娘を説得しますが、エリザベートはあきらめません。結局、皇帝のほうが折れます。皇太子ルドルフに情死された反省からか、孫娘には甘かったのか。
しかし、若いエリザベートがのぼせ上がった勢いで決めてしまったような、この結婚はうまくいかなかったみたいです。
のちのち、二人それぞれが愛人をつくったり、すっかり冷めきった関係に。
エリザベートの新しい恋人は戦争で死んでしまいますが、それでヨリが戻ることはなく、エリザベートはオットーと離婚しようとします。
「赤い皇女」社民党幹部と同棲
結局、離婚が成立するのは第二次世界大戦後のことですが、離婚に際して子どもを夫に取られそうになったところを助けてくれた社会民主党の幹部レオポルト・ペツネックと親しくなり、ついには同居。
社会民主党は共産党ほどの極左ではありませんが、基本的に君主制反対の党ですから、意外な組み合わせです。
エリザベートは「赤い皇女」と呼ばれました。
ペツネックの身分の低さはオットーどころではありません。まったくの庶民。幼くして両親を亡くし、孤児院で育っている苦労人でした。
しかし、その頃には皇帝は退位し、ハプスブルク帝国はもはやなく、エリザベートが誰と暮らそうが、ある意味で自由でした。
わかっちゃいるけど直立不動
1938年、オーストリアはナチス・ドイツに併合されますが、その少し前から国内右派の圧力が強まっており、「赤い皇女」エリザベートは社民党書記長の逃亡に手を貸したのではないかとの嫌疑がかけられ検事に尋問されます。
型どおり、身元の尋問から始まった。
父の名前は?
「オーストリア=ハンガリー帝国皇太子ルドルフです」
祖父の名前は?
「皇帝フランツ・ヨーゼフです」
そのことを承知で尋問を始めたのだが、検事はやはり立ち上がって、固くなり、不動の姿勢で頭を下げた。
こんなマヌケなシーンが本当にあったのか、と思いますが、本からの引用です。
ついこの間まで帝政だったのですから、皇帝の名は重いのでしょう。
19世紀末から第二次大戦後のヨーロッパ史を描く
『エリザベート ハプスブルク家最後の皇女』はエリザベートの一生を追いながら、19世紀後半から20世紀前半、ヨーロッパ激動の一世紀をみごとに描いています。ハプスブルク家の人とはいえ日本ではそれほど有名とは言えない一婦人の一生を追いながら、激動の近代ヨーロッパ史を生き生きと浮き彫りにしているのが見事。
エリザベートとは直接関係ない人物・出来事でも、時代の重要事項に関してはかなり詳しく書き込んでいます。
無味乾燥な権威筋のオーストリア史、中欧史を読むより、よっぽど前世紀への理解がすすみます。すでにこの時代の歴史に詳しい人には物足りないかもしれませんが、入門書としてはエリザベートやハプスブルク家に興味がなくてもオススメです。
なぜオーストリアは分割されなかったのか
連合国に分割統治されていたオーストリア
第二次世界大戦後、東ヨーロッパは次々と共産化され、ソ連支配下に入っていきました。
ドイツは東西に分断され、西ドイツは西側自由主義国の一員となりますが、ソ連占領地域(東ドイツ)は共産圏に。
オーストリアも当初、連合国に4分割統治されていたので、ドイツ同様に分断国家となる危険性がありました。
映画『第三の男』は分割統治時代のウィーンが舞台

分割統治時代のウィーンを描いた映画が『第三の男』。ロケが行われたのも1948年ですから、同時代です。
カンヌ映画祭でグランプリを獲得した名画ですが、当時の暗く荒廃したウィーンを描き出したこの作品はウィーンでは評判がよくなかったそうです。
映画のテーマ曲は日本ではエビスビールのCMでおなじみ。
したたかなオーストリア政府、統一を保持
戦前、オーストリアの中道政党はライバル党と対立路線をとったためにナチスに国を奪われてしまいました。その反省から、戦後はかつての対立関係を水に流して一致してソ連を出し抜きます。古株レンナーの知恵でソ連の息のかかった共産党を政府から排除していきました。
また、そもそも丸ごとソ連の勢力圏に入りそうだったのを四国分割統治に話を持っていったのはハプスブルク最後の皇太子オットーでした。国外で各国首脳とコンタクトを保ちオーストリアの独立を勝ち取るべく動いていました。これについては別書『ハプスブルク最後の皇太子 激動の20世紀欧州を生き抜いたオットー大公の生涯』に詳述されています。
影に日なたに国を守ろうとした人びとがいて奇跡的にオーストリアは共産化されることも、分割されることも、「敗戦国」の烙印を押されることもなかったのでした。

小国の悲哀
オーストリアは戦後、なんとか統一と自由を保ちましたが、帝国の一部(というか大部)であった東欧諸国はソ連の支配下で発展を阻害され苦しむこととなりました。
チェコなどナチスに蹂躙されても、大国は助けてくれなかったばかりか、そのナチスが去っても、ソ連がやってきて、ちっとも解放されませんでした。
ハンガリーはソ連に対して果敢に抵抗を試みましたが、外国からの応援はありませんでした。民主化運動は何万人もの犠牲者を出してつぶされます。
大国はナチスやソ連の横暴を非難するだけで、実際には困っている小国を見殺しにしました。
大国も自国を犠牲にしてまで外国を助けることはありません。口先だけの「信義」や「正義」を信じてはいけないのです。
ハプスブルク帝国の絆が「鉄のカーテン」に亀裂を入れた!
エリザベートは1963年になくなりますが、その後のヨーロッパについてもエピローグに。

1989年、ヨーロッパを東西に分けていた「鉄のカーテン」のほころびが真っ先に現れたのは旧ハプスブルク帝国内でした。
ハンガリーとオーストリアは、1980年代後半、すでにビザなしで通行可能だったのですが、東ドイツとハンガリーの間には査証協定があって、東ドイツ市民をハンガリー経由で西側に出国させてはならないことになっていました。
しかしハンガリーは協定を停止し、東ドイツからどんどん人が出国できるようにしたのです。
こうして「鉄のカーテン」に亀裂が入り、この年の11月には「ベルリンの壁」も崩壊します。翌年1990年には東西ドイツが統一し、1991年にはソ連邦が解体します。
大国のあっけない滅亡
大国の滅亡もあっけないものです。
480年続いたハプスブルク帝国は第一次世界大戦という誰も望んでいなかったのにマヌケの連鎖ではじまってしまった戦争であっけなく分解してしまいました。
この辺、どうマヌケだったかは倉山満『世界大戦と危険な半島』(KKベストセラーズ)がオススメです。
同時期、日本のマヌケっぷりは同じく倉山満が『史上最強の平民宰相 原敬という怪物の正体』に詳述しています。

戦後、ソ連はアメリカとしのぎを削る二大超大国のひとつでしたが、あれよあれよという間に崩壊してしまいました。
ソ連邦の後継国ロシアは、かろうじて「大国」の地位は保っていますが、けっこうボロボロ。
一寸先は闇。大国といえども未来永劫安泰ではないのです。
本の厚さを忘れるおもしろさ!
『エリザベート ハプスブルク家最後の皇女』(1992年発刊のハードカバー版)は二段組で400ページもあることから、すぐに本棚に戻されてしまいそうな本、あるいは、そもそも手に取られそうにない本ですが、読みやすい文章なので、読み始めると引き込まれます。
2003年には文庫化(上下巻)されています。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
なお、「エリザベート」のカタカナ表記には「エリザベト」や「エリーザベト」など揺れがありますが、本に従って「エリザベート」としました。